


「無人化」は中止し、安心・安全な公共交通をー 西武鉄道に要望書を提出

水道はいのちの問題ー料金引きあげ撤回署名29000筆提出

戸田市議団が県水値上げ撤回の署名を県議団に手渡す
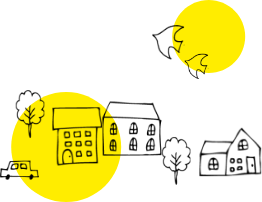

11月17日 前原県議は春日部市民文化会館で、埼玉県庄和高校の学生たちと一緒に、演劇を観劇しました。
 ←春日部文化市民会館にて
←春日部文化市民会館にて
劇団青年劇場による「きみはいくさに征ったけれど」というタイトルの公演でした。
今を生きる高校生 宮斗は学校にも家にも居場所をみつけられず、死んでしまいたいと思ってマンションの屋上にいたところ風変わりな青年が現れます。「なんしとん?」と軍服姿で現れた幽霊の竹内浩三が話しかけます。
戦争で亡くなった三重県出身の竹内浩三は実際にいた方で、1945年4月にフィリッピン・ルソン島で23歳の若さで戦死された実在の方です。軍国主義一色の窮屈な時代に生き、戦地においてもみずみずしい感性で詩をたくさん残しました。
浩三と話をしている宮斗がポツリと言います。「僕・・・なんのために生きているのかわからないんだ」
浩三は「わからんっちゅうことも、生きとることになるんとちゃうか?」と応えます。
その後学校でのいじめや「いじめはないという」担任の若い男性教諭。早くに夫を亡くし女手一つで宮斗を育てた母親にも新しいパートナーができて、ますます居場所がなくなっていく宮斗。
そんなある夏休みに母の勧めでおばあちゃんが暮らす父の故郷、三重県の伊勢に向かった宮斗。車中で「浩三」と名乗る青年に話しかけられる。自分も伊勢に行くという。
久しぶりに再会した祖母や伊勢で出会った温かい家族、そして浩三との出会いで宮斗のこころが少しづつほぐれ、「生きることが楽しかった君と僕は出会えた」とクライマックスを迎えます。
高校生の方たちもみんな硬唾をのんで物語の進行を見守ってました。
主人公の年齢も自分たちに近いので、主人公の葛藤が手に取るように伝わってきたことと、生きてることが楽しいことだという言葉に学生たちも共感してました。
観劇が終わり、前原議員から学生の方に「家族で芸術などに行かれる機会はありますか」との質問に「家族では観劇はしたことない」との答えでした。
庄和高校は毎年芸術に触れる機会を設けているそうです。3種類の芸術(演劇・伝統芸能・音楽)などです。
3年間で必ずどれか1度は芸術に触れる機会を設けてます。今回の学生の方の感想として「生きることを考えさせられた。戦争について考えさせられた。主人公の年も自分たちに近いので、気持ちがよくわかる。」
そのほかに演劇部学生の学生のかたの感想として、「初めてプロの演劇をみた。1つの舞台で空間の使い方上手で、強弱が素晴らしかった」との感想もありました。
前原議員から学生の方に「年に一度の芸術に触れる機会が更に増えた方が良いですか?」との問いに「機会があれば年に二回はやってほしい」との答えでした。
学校の先生からは「会場に来て生徒たちが直接芸術に触れることは感性を育てるのに大切なことである。昨年はコロナ禍であったが何とか芸術に触れることが出来た。ぜひこれからも続けていきたい」
前原議員も「文化芸術は生きる力である。文化芸術の火を絶やしてはいけない。今後もしっかりバックアップができるよう県に働きかけていきたい」と述べました。