


水道はいのちの問題ー料金引きあげ撤回署名29000筆提出

戸田市議団が県水値上げ撤回の署名を県議団に手渡す

八潮道路陥没で、におい・振動つらい。一時避難したい
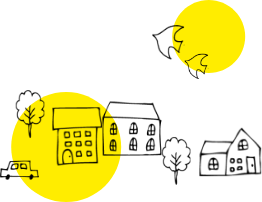

11月12日村岡・柳下両県議は、埼玉県内の青年団体である民主青年同盟埼玉県委員会=「みんせい」の役員と懇談しました。
みんせいはコロナ禍の中で、学生たち向けのフードパントリーを大学周辺駅20か所で行ってきました。
コメ2キロとレトルト食品、ポカリスエットのセットを約900袋を配布し、総コメ量は1・8トンに上ります。
SNSなどで呼びかけ集まった寄付、約100万円がその原資です。
とりわけ、11月に入ってから行った西部の駅では100人ほどが来場。過去最高となりました。
第2波とよばれる夏の時期より、むしろ増えてきている印象だそうです。
「みんせい」は、食料を配布すると同時に生活状況アンケートに取り組み、200人もの声が寄せられています。
大学はオンライン授業「つまらない」「課題が多すぎ」「寂しい」
コロナ禍で大学は閉鎖。オンライン授業となり、現在もオンラインと対面の併用が多いといいます。
オンラインは、教授も不慣れで、「スライドをただみるだけ」「操作を教授が生徒に教えてもらっている状況」
しかも、授業のたび「600字の感想文を書く」など課題が出されます。1週間ですべての授業で課題がでると大変な量となり、学生は課題に追われます。
友達もできず、毎日誰とも話をしない日々が続き、孤独感も募ります。1日で「コンビニの店員としか会話しなかった」という日も。
特に1年生は、入学以来「1日も大学へ行ったことがなくて、大学生になった実感がしない」
バイトは減り、光熱費はかさむ、食事は1日1食
フードパントリーを開始する前から飛んできて「バイトがなくなって、学費が払えないので、1日1食で暮らしている。
どうしたらいいのか、わからない」と訴える女子学生も。
「次に何を食べるかばかり考えている」
「もやしは学生の味方」「納豆・豆腐は学生の味方」
自宅でオンライン授業を受け続けるため、光熱費がかさみます。1日の最も暑い2時間だけエアコンをつけてもいいルールにしている人も。
対面授業を全面的に復活させてほしい。
これが、みんせいの要望です。
また、
学費を引き下げてほしい。ということです。
国の学生支援給付金は、あまりに条件が厳しく受けられる学生がごく一部です。
特に、大学の窓口で却下される例が多いそうです。
こうした活動を報告し、みんせいの佐藤和馬埼玉県委員長は
「今年を、大学生にとって、空白の1年としないよう、
国などへも支援を働きかけていきたい」と語りました。
また、柳下礼子団長は
苦境に追い込まれて「誰かに相談したい」という学生に対して相談できる機能が必要だ」
村岡県議は「学生がおかれた状況をしっかり県に伝える必要がある」と語りました。